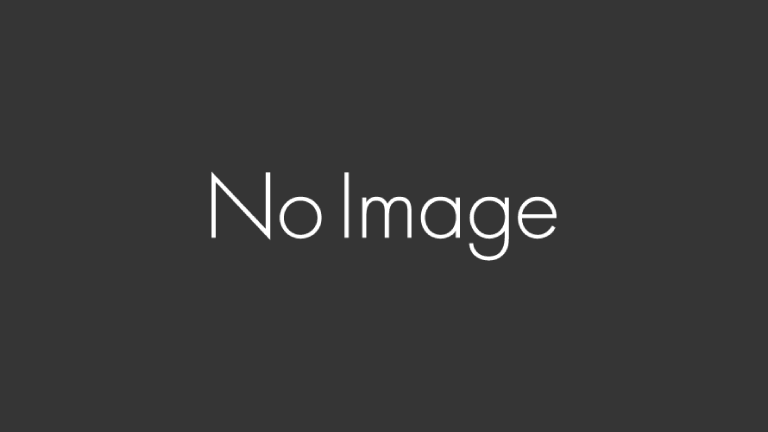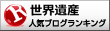東照宮とは
東照宮とは、東照大権現(徳川家康)を祀る神社です。
家康は死後に神と同等に崇められる存在となり、その「東照大権現」を祀る東照社(後に東照宮に格上げ)が作られました。
東照宮は、将軍家によって創建された日光や久能山の他、御三家や各藩主によって全国各地に創建されました。
東京の上野にも上野東照宮があり、六人の徳川将軍が眠っています。
話がややこしくなってきましたが、世界遺産になっているのは日光東照宮だけです。
世界遺産、全部行ったら海賊王!
日光の社寺(Shrines and Temples Nikko)
1999年登録
2017年5月5日
所用で東京に行くことになったため、東京から電車でGO!
東京からの行き方はいくつかありますが、JR日光駅か東武日光駅を目指しましょう。
両駅は隣り合っています。

そしていざ1200年続く聖地へ。
世界遺産「日光の社寺」には、東照宮、二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)、輪王寺(りんのうじ)の二社一寺に属する建造物103棟が登録されています。
日光東照宮は、栃木県日光市にある江戸幕府初代将軍「徳川家康」を神格化した東照大権現を祀る神社。
世界遺産「日光の社寺」の中心的な構成資産で、日本全国の東照宮の総本社的存在である。
正式名称は「東照宮」ですが、他の東照宮との区別のために、「日光東照宮」と呼ばれることが多い。
「権現造り」という建築様式の完成形とされています。
公式Webサイトによると、平成9~36年(令和6年)度まで「平成大修理事業」中。
「陽明門」は平成の大修理を無事に終了。
見どころの「三猿」「眠り猫」の塗りなおし修理も合わせて完了したということで訪問決定。
日光東照宮は、日光霊峰の山懐聖地恒例山にあり、中禅寺湖から流れる大谷川と女峰山から流れる稲荷川との河合いの山岳水明の地に…
そして当日、ゴールデンウィークなので、やはり多かった…
日光駅からだと歩いて2kmもないので、歩ける人なら歩いた方がいいです。
東照宮の駐車場から駅までは、朝8時前から渋滞していて、車は一日中詰まってました。
多分この日だけで数万人の観光客が来たと思います。
※コロナ前の話です
日光東照宮

その前にこういうちょっとマイナーな場所もちゃんと行ってます。

家康公の書、愛用品をはじめ、朝廷や大名からの贈り物、「 東照宮縁起五巻」(狩野探幽)、重要文化財である家康公着用の「南蛮胴具足」や名刀「勝光宗光」を収蔵。
さらには「寛永の大造替」の上棟祭に用いられた「大工道具および箱(国宝)」、家康公御画像など歴史的にも美術としても貴重な品々が数多く展示されています。
国宝の大工道具とは…恐るべし日光。

新緑の季節だったので、緑がきれいでした。
春は満開の金剛桜、秋には中禅寺湖の紅葉、冬は男体山の雪化粧と、日光は四季折々で様々な姿を見せてくれます。
この五重塔の標高は630~640mです。
2012年に開業した「東京スカイツリー」の高さ634mとほぼ同じ。
この2つの塔は、同じ沿線で頂点がほぼ同じ高さに位置。
さらに五重塔の優れた免震技術は、スカイツリーの心柱制振というシステムの参考にされているという共通点もあり、東京スカイツリーのオープンに合わせて、五重塔の内部が初公開されています。
日光東照宮と東京スカイツリーのコラボとは、徳川家康でも想像できなかったであろう。

象を見たことがない狩野探幽(1602-1674)が下絵を想像で書いた象と言われています。
象が初めて渡来したのは、江戸中期の享保十五(1730)年の五月、中国の商人が連れてきたそうです。
三神庫には、祭器や渡御祭の装束が収められています。

「猿が馬を守る動物である」という伝承から来ているようで、元は西遊記の弻馬温では?
弻馬温(ひっぱおん)とは
孫悟空が天帝に与えられた役職で馬屋の番人のことです。 この役職の地位が低いと知って、悟空はブチ切れるわけですが…
さて、この8枚の中に描かれている猿の一生は、人間の平和な一生の過ごし方を説いたものとなっています。
8枚の中で最も有名な「見ざる、言わざる、聞かざるの三猿」
これは自分に不都合なことは見ない、言わない、聞かない方がいいという教えのようです。
勉強になります…

守られている馬も、いる時といない時があります。
運がよければ会えるでしょう。

門全体が膨大な数の極彩色の彫刻で覆われ、見ているうちに日が暮れるので、「日暮御門」とも言われている日光東照宮を代表する門です。
名前の由来は「平安京大内裏外郭十二門」のうちの「陽明門」から。
寛永の大造替(1636年)で完成。建築形式は「三間一戸楼門」で、屋根は入母屋造、銅瓦葺き。
東西南北の各面に「唐破風」を付しています。
東照宮全体が山の地形を活かした造りとなっています。

陽明門、表門、回廊、唐門、拝殿、本殿などにも数多くの彫刻があり、その総数は5173体!
そのうちの508体は陽明門にあります。数えた人、大儀であった!
中国の伝説や故事の人物彫刻や、霊獣、霊鳥と呼ばれる吉祥的な彫刻ばかりです。
徳川家康を「神」として祀る社殿において、さまざまな象徴的意味を持っています。


この眠り猫は、「家康公を護るために寝ていると見せかけ、いつでも飛びかかれる姿勢をしている」
または「裏で雀が舞っていても寝ているぐらいに平和」という説があるようです。
「裏雀」は人が多すぎて撮れませんでした…
左 甚五郎(ひだり じんごろう)は、江戸時代初期に活躍したとされる伝説的な彫刻職人だが、実在の人物かは不明。
優れた工匠の代名詞として使われたという説もあり、左の由来にも諸説あるようです。
そして眠り猫の門をくぐって、家康公のお墓である「奥宮」へ…
日光東照宮・奥宮

奥宮御宝塔の前に建てられた高さ3.4m、柱間2.5mの銅製の唐門です。
1650(慶安3)年に狛犬(重要文化財)と共に鋳造されています。目力が凄い狛犬です。
もともと門は石造りだそうですが、地震により崩壊したため銅製に造り替えられています。
狛犬は創建当時は木製でしたが、その後石造となり、鋳抜門が再建された際に銅製に造りかえられています。

奥宮は家康公が眠る場所とされ、歴代徳川将軍のみ立ち入りが許された、日光東照宮で最も神聖な場所です。
家康の遺言は、
「遺体は久能山に葬り、徳川家の菩提寺である増上寺で葬儀を行い、三河の大樹寺に位牌を納め、一周忌の後、日光山に小堂を建てて勧請せよ、八州の鎮守になろう」(『本光国師日記』より)
と久能山東照宮のwebサイトに書かれています。
江戸城から見て、南にあるのが増上寺、北東(鬼門)に神田明神と寛永寺。
そして北にあるのが日光東照宮なのです。
北は北極星の方角で、北極星は天帝、最高神とされています。
久能山で神として再生した家康(東照大権現)が江戸を守護するために日光に東照宮が建てられたようです。
壮大なスケールの話です…
話は変わりますが、2021年7月16日~9月5日、福岡市博物館にて「特別展・徳川家康と歴代将軍~国宝久能山東照宮の名宝~」が開催されたので訪問しました。
久能山東照宮というのは静岡県にあります。
重要文化財「ソハヤノツルキ」という久能山東照宮第一の重宝の太刀も見れました。
作者は、国宝で天下五剣の一振りでもある「大典太光世」と同じ光世の作と言われています。
光世は三池(福岡県)の刀工なので、福岡に里帰りしたわけです。
三池と言えば世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の一つ、三池炭鉱(万田坑・宮原坑)、三池港もあります。
話を奥宮に戻す!
1965(昭和40)年の「三百五十年式年大祭」では、特別に一般公開されています。
この下に家康公の遺骸があるとされていますが、誰も見たことがないため、謎とされているようです。
最も大混雑したのが、「陽明門」から「眠り猫」を通り、「奥宮」まで行く道程…
多分往復で1時間近くかかってます。まるで議員の牛歩戦術の如しでした。
どれぐらい混んでたかと言うと…

奥宮からの戻りはこの大混雑…階段が続きますが、一歩ずつしか降りれません。

朝早く来ていてよかったです。昼過ぎの陽明門横はこの状態…




日光東照宮の白は、家康を神格化するための特別な色。
家光の眠る輪王寺大猷院には、白は使われていません。




そうこうしているうちに、もう一つの世界遺産、二荒山神社に足を踏み入れていました。
二荒山神社
標高2486mの男体山を中心に2500メートル級の山々が連なる日光連山。
太古から噴火を繰り返してきた男体山が作ったのが1300mのところに位置する天空の湖、中禅寺湖。
さらに日本三大瀑布の一つ、華厳の滝があります。高さ97メートルの高さから落ちる水量は毎秒3トン。
冬はこの華厳の滝の周りが凍って、えもいわれぬ光景が広がっているようです。
日本三大瀑布、残りの二つは世界遺産・熊野にある「那智の滝」と茨城にある「袋田の滝」。
滝が流れ落ちる先は大谷川(だいやがわ)。河岸には男体山の溶岩が固まった岩が多数見られます。
男体山の大谷川と女峰山の稲荷川、 華厳の滝から10kmほど下った2つの川の合流地点、このパワースポットにあるのが「日光の社寺」なのです。


この行列なので撮影のみで素通り…



二荒山神社は、767年に勝道上人が建てたといわれています。1250年以上も前の話です。
江戸時代初期、天海僧正により日光東照宮が建てられると、二荒山神社も多くの人々から崇敬されるようになり、その後は、二代将軍徳川家忠により本殿が再建されました。
二荒山の由来は、男体山に登った勝道上人が、その景色を浄土にある補陀落(ふだらく)に重ねて呼ぶようになったと言われています。
補陀落(ふだらく)→ 二荒(ふたら)→二荒(にこう)→日光(にっこう)と繋がるようです。
なるほど、なるほど。
輪王寺
輪王寺本堂は、東日本最大の木造建築物で、平安時代に創建された希少な天台密教形式のお堂です。
現在の建物は、三代将軍家光公によって建て替えられ、三仏堂の前には、推定樹齢500年という、天然記念物に指定されている「金剛桜」が植えられています。
中には、千手観音、阿弥陀如来、馬頭観音の三体の高さ約7.5メートルの大仏様が!※撮影禁止
さらに薬師如来、阿弥陀如来、釈迦如来という掛仏の、二組の三尊仏がご本尊さまとして祀られています。

2017年はまだ修理の真っ最中 この大きな木が樹齢500年の金剛桜
金剛桜はヤマザクラの突然変異と言われています。5月5日に行ったので、ちょうど散った後のようでした。
平成の大修理は長引きましたが、令和2年3月で終了。13年ぶりに建物が姿を現しています。


日光東照宮を現在のような絢爛豪華な姿にしたのが、三代将軍徳川家光。
その家光がこの輪王寺に眠っているのです。

拝殿内部は非公開ですが、2020年4月21日〜2022年3月31日まで特別公開されました。
次はいつになるかわかりませんが、公開時が訪問時です。
世界ふしぎ発見で内部を見ましたが、とにかくゴージャス!!
金だらけなので、金閣殿とも呼ばれるそうです。



日光廟大猷院は、家光の霊廟で、四代将軍家綱が建造。大猷院とは家光の法号のことです。
日光復活物語
江戸時代には人が絶えなかった日光。明治時代になり、幕府の援助がなくなると参拝者が激減。
その後、今のような観光名所へ復活を遂げたのは、外国人、特にイギリス人のおかげだったそうです。
イギリス人は日光を大絶賛。中でも明治5年に訪れたアーネスト・サトウは、輪王寺大猷院を「日光の宝石」と称え、出版したNIKKOのガイドブックはベストセラーに!
そして現代
京都の世界遺産巡りをした時に会った外国人は、京都のあとはニコに行く!としきりに言ってました。
そう、ニコ=日光です。




かなりの広さなので、見るのに2日を予定していましたが、朝8時から夕方5時までひたすら歩き回ったので、見所はすべて制覇できました。1日あればなんとか全部回れます。
世界遺産には建造物103棟が登録されています。全部行ったか数えてないのでわかりませんが、OKでしょう。
宿は2泊取ってましたが、2泊せずに2日目の朝にすぐ東京に戻りました。
このあたりは宿も少ないので全然予約が取れず、やっと取れたのが外国人向けのドミトリーのゲストハウスのみでした。
というのも夕方5時以降はほとんどの店が閉まり、食事の店なども本当に少ないので、関東の人だったら、日帰りでもOK牧場です。
この4ヶ月前に膝靭帯を断裂する大怪我を負ってましたが、歩行は回復していたのでよいリハビリになりました。
迷わず行けよ、行けばわかるさ、東照宮